人権教育
本校の人権教育
本校で人権教育の取り組みを随時紹介していきます。
平成26年度の人権教育関連取り組み予定
◎校長による人権講話、人権に関する学年集会、仲間力ポスター掲示、三中・四中1年生合同自然宿泊体験教室(4月〜7月) ◎道徳授業地区公開講座(9月) ◎セーフティ教室(11月) ◎1年人権教室(11月) ◎いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議(11月) ◎人権講演会(12月)
校長による人権講話(6月9日朝礼)
6月は、「ふれあい月間」として、いじめをなくすため生徒に注意喚起していく取り組みを行います。その第一歩として、9日(月)の朝礼で、校長より、いじめを認めない環境を作っていこう。そのためには、からかいなどいじめにつながるような行為をお互いに注意しあえるようにしようと呼びかけをしました。2月25日、朝日新聞に載った兵庫県の主婦の方の投書の記事を生徒に紹介し、投書に書いてある小学生のような態度をとってほしいと話し、考えてもらうようにしました。以下、その投書を紹介します。 「息子は小学生の頃、おもしろい、クラスのいじられキャラだったようで、本人もそれを楽しんでいた。ある日の休み時間、いつものように教室で友達数人とふざけていたら、いじりがエスカレートし、息子がもうつらいと思ったことがあったらしい。その時、「もうええやろ、やめたれや」と言って、家が近くて仲の良い友達が止めてくれた。 体が大きく、野球をしているその子は、嫌なムードの教室から「行こうぜ」と息子を連れ去ってくれた。「ありがとう」と息子が言うと、「えっ? なんで?」と言って笑ったらしい。 その後、私も彼に「あの時はありがとうね」と言ったが、恥ずかしそうに笑った。彼のお母さんにもお礼を言ったら、「そんなことがあったんですか。きっと息子はそれが正しいと思ったんでしょうね」と笑った。 そんな風に育てられたから真っすぐなんやなと私は感心した。今でも感謝している彼は田中将大君。大リーグ、ヤンキースの投手として一歩を踏み出した。」
|
|
人権教室
|
|
|
セーフティー教室
|
|
|
いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議
|
|
|
人権講演会
|
目黒区小・中学生人権啓発標語作品展への出品優秀作品紹介
本校より、目黒区小・中学生人権啓発標語作品展に出品した人権標語の優秀作品を紹介します。全員参加で取り組みましたが、それぞれが思いを乗せた標語となりました。優秀作品については、3月2日に人権擁護委員の方から表彰状を伝達していただきます。
●人権擁護委員賞「守りたい 笑顔がきっとそばにある」【2年B組女子】
●「やめようよ 見て見ぬフリも 偏見も」【1年A組女子】 ●「考えよう 人の心 自分の言葉」【1年B組女子】
●「悪口を 一緒に言ったら その仲間」【2年A組男子】 ●「『からかい』は 冗談でも 許さない」【2年F組男子】
●「一人一人の優しさが 一番の強さになる」【3年A組女子】 ●「人との違い それを認められる人になろう」【3年B組女子】
平成25年度の取り組み紹介

|
人権講演会
|
|
|
いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議
|
|
|
人権教室「お肉の情報館見学」
|

|
セーフティー教室
|
|
|
道徳授業地区公開講座
|
三中・四中1年生合同学年集会

|
いじめのない統合新校に向けて、7月9日(火)第1回目の三中・四中の交流活動が実施されました。統合前からの人間関係作りをひとつひとつ積み上げていきます。次回の交流は、12月に四中で行います。詳細は統合新校に向けてのページに記載しています。 |
平成24年度の取り組み紹介
平成24年度の取り組みは下記のとおりです。
地域・保護者・生徒と共に命の大切さを学ぶ教室

|
2月27日(水)人権教育の一環として、「地域・保護者・生徒と共に命の大切さを学ぶ教室」を開催しました。今回は警視庁犯罪被害者支援室及び目黒警察署の協力を得て、実施しました。 講師の佐藤咲子さんは、1964年、15歳の高校生の時に、岩手県でご両親を猟銃強盗殺人事件で亡くされました。犯罪被害者の立場からの「命の意味と大切さ」や、「親の大切さ」「兄弟(姉妹)の大切さ」についてのお話をうかがいました。特に、何年経っても癒えない心の傷のお話や、被害者遺族で、ひとつも悪いことはしていないのに自責の念にかられていたというお話は、涙を誘いました。 生徒には、「どれだけの月日も心を癒さない。自分の責任と無関係に、大きな傷を負い懸命に生きる人たちがいることを知ってほしい」「いじめや家庭内の悩みなどで、苦しんでいる人もいると思う。1人で悩んだり、見て見ぬふりをせず、周りに話をしてほしい。絶対に命を絶たず、今日を一生懸命生きてほしい」「あたりまえのように思っている、家族と一緒に過ごせる今日に感謝してほしい」というメッセージをいただきました。 |
人権講演会

|
12月13日(木)、6校時、人権講演会が体育館で行われました。参観日ということもあり、大勢の保護者の方々においでいただきました。講演会では、目黒区教育委員会の人権教育担当の指導主事からのお話と、生徒が人権について考える活動を行いました。先日行われた「いじめ問題を考えるつどい」の取り組みを前提に活動が実施されました。ワークシート等を使って行われ、生徒も積極的に記入していました。 |
保護者会〜いじめ問題を考える〜

|
12月13日(木)、いじめ問題を考える保護者会がランチルームで行われました。今回は携帯電話を悪用したいじめについて焦点をあて、保護者と一緒に考えを深めました。まず、校長より、インターネットを悪用したいじめの種類といじめを未然に防ぐための保護者の対応方法について、関係団体の作製したパワーポイントを利用した説明があり、その後、警視庁のサイバー犯罪対策課の作製した『TRAP』の「傷ついた心」を視聴し、インターネットを悪用したいじめの実態を学習しました。最後は意見交換を行いました。 |
いじめ問題を考えるつどいを開催しました。

|
11月30日(金)、三中の2年生と下目黒小・田道小の5年生が集まり、「いじめ問題を考えるつどい」が開かれました。グループに分かれて各教室で、いじめ問題について話し合いを行いました。中学生が司会をし、一人一人の意見を発表し合い、黒板にまとめていました。話し合いの結果を発表用の模造紙に書いて、その後、体育館で写真のように各グループのまとめを発表しました。各グループで作成した発表用の模造紙は各校に分けて、それぞれで掲示します。なお、参加した2年生の感想を書いた学年だよりは、下記のリンクから見ることができます。 |
人権学習:『お肉の情報館』(人権教室)
11月20日火曜日、人権教育の一つである、『お肉の情報館』への見学に第一学年が行ってきました。肉が我々の口に入るまでのこと、それにともなう差別的な出来事等人権に関することも学習してきました。詳細はまとめを出します。
校内人権研修会を開催しました
11月8日(木)、目黒区教育委員会教育指導課の統括指導主事を講師に招き、教職員向けの校内人権研修会を行いました。目黒区人権尊重教育推進員会の発行した「人権尊重教育推進委員会だより」などを教材にして、「いじめに対する正しい認識」や「いじめ加害に影響する3要因」について研修を受けました。さらに「いじめを防ぐ工夫と意識」について、工夫としてどの生徒も落ちつけて、生徒同士が絆が作ることができる居場所づくりが大切になるという説明を受けました。
道徳授業地区公開講座

|
9月15日(土)、道徳授業地区公開講座が行われました。5時間目は、道徳の授業参観を行い、終了後、保護者の方と教員が協議会を行いました。授業は、各学級ごとに工夫をこらし、「生命尊重」・「思いやる心」・「家族の敬愛」など人権にも関わるような題材で取り組みました。家族の敬愛をテーマに授業を行った学級では、生徒から「家族がそろっている普通のことに感謝している」というような意見が出ていました。協議会では、駒澤大学の杉崎先生にお話をしていただき、子どものほめかたについて保護者との意見交換ができました。保護者と教員で共に道徳を考える機会となりました。 |
「ならぬことはならぬもの」(夏休み後の学校生活について)
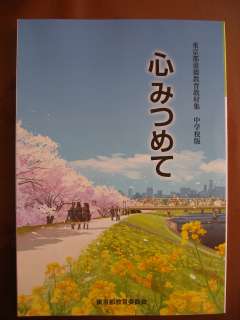
|
8月27日(月)の全体集会で、全生徒に向けて、夏休み後の学校生活についていくつか話をしました。29日(水)に全生徒に東京都道徳教育教材集「心みつめて」を配布しましたが、その中の江戸時代に会津藩士の子弟教育で使われていた「什(じゅう)の掟」を紹介しました。中でも、「虚言(うそ)を言うことはなりませぬ 卑怯な振る舞いをしてはなりませぬ 弱い者をいじめてはなりませぬ ならぬことはならぬものです」と言う言葉を強調して伝えました。弱い者いじめなど、人として、絶対やってはいけないことがあるということを改めて生徒につたえました。「心みつめて」は各ご家庭に一度持ち帰るよう生徒に伝えましたので、保護者の方もご覧になって下さい. また、人権作文を夏休みの課題として全生徒に提出させています。一人一人の生徒が人権を考える機会となります。夏休み後も、人権学習は継続して行っていきます。(校長より) |