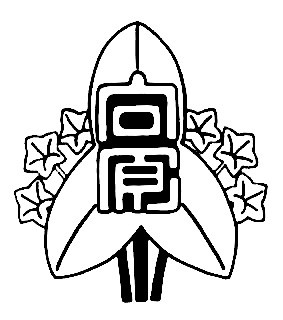校内研究
令和7年度 校内研究
研究主題
- 問題解決の見通しを振り返る指導の充実 ~算数科の授業を通して~
- 児童が安心して学校生活を過ごすことができる人間関係・教育環境づくり
- 児童が自らの学び進める力の育成「自己調整学習」
(1)研究の方向性
①算数科の授業展開を目黒区が研究開発として行っている「自己調整学習」の視点から捉え直し、児童自らが学びを進める力を育成する。(「よく考える子」、「かかわりを大切にする子」の育成)
②学習指導要領に記載される「主体的・対話的で深い学び」を行うためには、特別活動の資質・能力(協働の知識・技能、合意形成・意思決定の能力)の実現を通して、学級の児童同士の人間関係を形成していく必要がある。講師の先生をお呼びして「児童の人間関係づくり」について学び、児童同士のつながりを深め、「主体的で・対話的で深い学び」に生かしていけるようにする。
③「チャレンジタイム」の際に、各学年で調べ学習の大テーマを設定し、それに関する小テーマを児童が選択して調べ学習を行う。そして分かったことを発表する。【探究学習】さらに、探究学習の中で行われている「自己調整学習」にも注目して、児童自らが学びを進める力を育成する。
低学年→個人で調べ学習を行い、分かったことを発表し合って、考えを広げる。
中学年→個人で調べたものを持ち寄って考えを繋げていき、分かったことをグループで発表する。
高学年→個人で調べたことを学級や学年で伝え合うことを通して考えを深め、新たな考えを創造していく。
探究課題の例
1年→動物
2年→植物、世界の遊び
3年→職業(見学したものを中心に)
4年→自然、職業
5年→環境、伝記をもとに人物紹介
6年→職業調べ
実施回数…1単元(発表も含む)12回程度【目安として】
(2)研究の進め方
低、中、高の分科会ごとに1回ずつ研究授業を行い、算数科における自己調整学習の授業展開を学ぶ。
講師の先生の講演を聞き、児童が安心して学校生活を過ごすことができる人間関係・教育環境づくりの基礎を学ぶ。
学期末にチャレンジタイム(自己調整学習)の実践報告会を行い、向原小としての系統性のある指導パターンを作成する。